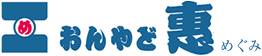湯河原温泉 おんやど恵トップ > 小説「湯けむり」 > 第十一話
客がふえるにつれて久子たちはふとんつくりに追われた。新しくつくるだけでなく、古くなって汚れたふとんは洗って干して中身を入れ替えた。夏の暑いさなか、汗みどろになって綿ぼこりにまみれて働いた。
「終わったらキネマ連れてってやるからね」
暑さと汗と疲れでダレそうになるとあきがやってきてそう言った。あきは決して「働け」という言い方はしなかった。ノンちゃんもユキちゃんもそのひとことで気を取り直した。
湯河原にはキネマという名の映画館が一軒だけあった。そこで映画を見て帰りにラーメンを食べるのがあきのごほうびだった。その頃はラーメンを取り寄せて食べることなど考えられなかった。映画とそのラーメン一杯がうれしくてみんな夢中で働いたのである。
夜、女中部屋に帰って寝る前に久子たちはあきの部屋へいって膝を折り「おかみさん、おやすみなさい」とあいさつしてから眠りにつく習慣になっていた。
ソフトクリームの出始めの頃である。久子たちはあきにあいさつをすませると窓からぬけ出してソフトクリームを食べに行った。もぬけのからになった女中部屋へあきが心配してのぞきに来た。
望みをとげて久子たちが窓から入ってくるとあきが部屋の中に座っていた。
「三人ともそこに座りなさい」
「すみません」
久子、ノンちゃん、ユキちゃんと三人の女中は肩をすぼめると一列になってあきの前に座った。
「謝る前に聞きなさいよ。窓から出入りするなんて娘っ子のすることだかね。まして夜道を娘っ子だけで歩くなんて、万一のことがあったらどうするだね」
「すみませーん」
三人は揃って頭を下げた。
こってり油を絞られた翌日は、三人は決まって一日中口をきかなくなった。忙しすぎる。少しぐらい自分たちで遊んで歩く時間があったっていいだよ。そんな気持ちがだれの胸にもあったからである。
その晩あきのところへ就寝前のあいさつに行くと「これお食べ」と言うとあきは菓子の包みを差し出した。それでノンちゃんやユキちゃんの気嫌はたちまち直った。
たあいないといえばいえる。久子にはそんな二人が妹のようにも想え、あきは母親のように感じられた。恵旅館の面々は家を失った久子にとっては新しい家族だった。
が、ここは父親のいない家族だった。良平は青ペン、赤ペン、白ペンなどと呼ばれる赤線に〈恵〉というパンパン屋を出していて、〈恵〉の女を連れては熱海へダンスをしに通っていた。朝五時に出て夜の十時まで客取りに各地をまわってきたあと遊びに出るのである。ときには最終列車の行ったあと線路伝いに熱海まで歩いて遊びに行くこともあった。こんなときはむろん一人だった。良平のダンス上手のダンス好きは姿に似ず定評があった。
「ここのウチは旦那がいねえのかい」
なじみ客さえそう言って首をかしげた。良平の酒嫌いも相変わらずだったのである。