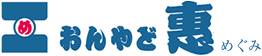湯河原温泉 おんやど恵トップ > 小説「湯けむり」 > 第十三話
芸者ふさこが湯河原へ来たのは昭和三十二年九月一日のこと。この年の四月売春禁止法が実施され青ペン、赤ペン、白ペン、新世界などの赤線が大揺れに揺れているときのことだった。猶予期間の切れる来年四月一日には湯河原名物赤線の灯もいよいよ消えるというその最後のまたたきが、ふさこの目にはこよなく美しく見えた。
芸者が身を置く花柳界と赤線の間には明瞭に一線が引かれていたが、地の利からいえば互いに無縁ではありえなかった。宴席にはパンパンが酌に出ることもあったし、ふさこたち芸者衆が客を赤線に案内して行って「じゃあね、おあとはよろしく」と引き渡して帰ることもあった。
その赤線の灯もあくる年の四月完全に消えた。それからというもの座敷を終えて帰る夜道で、ふさこはよく男に抱きつかれた。赤線の灯は消えても一度火のついた男たちの欲情の火はなかなか冷めないようであった。
「赤線がなくて困るのは芸者も同じよ」
ふさこはあきにそう言ってこぼした。座敷が乱れて困るというのが芸者衆の一致した感想だった。
当時の芸者は百人を越す程度の数で古株は昭和二十三、四年頃から湯河原に来た姐さんがたである。年齢も出身地も本当のことをいわないのが芸者衆の常だが、古株は小田原の宮小路あたりから移った芸者であった。栄家の松栄などがその流れである。
三味も謡も習った古参の芸者に比べふさこは不器用で三味も謡もよくはしなかった。あきがいくら手ほどきをしても覚えようとしない。
「いいのよ、おかみさん。あたしゃこの社会に面白半分で入ったんだから」
そんなことを言っていて座敷に出ると「ハイヨーあたしのラバさんだよッ」と一枚ずつ脱いでいって裸になると扇子二本で前を交互に隠して客を喜ばせていた。芸としては上品ではなかったが、客を遊ばせるのはうまかった。座敷のにぎやかしには重宝した。
客が酔っ払ってクダを巻いても嫌がらずになだめたし、時間かまわずに居てくれてそれでいてあらかじめ決まった玉代しか取らなかった。そういう意味では毛並の変わった芸者といえた。
「なんだいあの顔のまずい芸者、ここ来るといつもいるな」
目時浅太郎はあきをつかまえてそう言った。恵旅館はいまや鳶とテキ屋の定宿のようになっていた。
客がとくに芸者を指名しない限りどこの置屋に声をかけどの芸者を呼ぶかは旅館側の裁量である。いっぺん入れて客のウケの悪かったような芸者はまず声をかけない。芸者は芸が売物だがある面では人気商売である。ふさこはあきのウケがよかった。これはと思うととことん面倒を見るのがあきの性分だった。
浅太郎も恵旅館へ来るとふさこを呼んだ。はじめて呼ぶのを初回、二度目はウラを返すといい、三度目からおなじみといってはじめてお客さんと呼ばれるようになる。浅太郎をはじめ鳶の頭連中は軒並みふさこのなじみになった。頭連中の座敷になるとふさこは時間まで芸者をつとめ、いったん帰ると着替えて戻り朝までバクチの世話をやいて一緒に遊んだ。