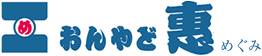湯河原温泉 おんやど恵トップ > 小説「湯けむり」 > 第十五話
愚痴をいう、からむといっても仕事上のウサにすぎない。芸者をやっていて芸者稼業が大変だなどと思っている芸者はひとりもいない。さいきんは金を稼ぐ目的で芸者になる若い女がふえてはいるがそれも嫌でなるわけではない。歌って踊ってハシャいで座をにぎやかせてそれでくらしてゆけるのだから金を払って同じことをする客と比べれば月とスッポンである。さいきんの客は遊びを知らなくなったといっても、それは夫婦で来て芸者を三人もあげて奥さんを楽しませ自分はそれを見て喜ぶような粋な客が少なくなっただけである。ご祝儀をくれる客が減ったといってもそれは唯単に時代の流れ。玉代を払えば客は客である。客に感謝するのを忘れないようにしようとふさこが自分に言いきかせるようになったのも恵ホテルのおかみのおかげだった。
ふさこは湯河原のというよりも恵ホテルのといってもよいほどあきに目をかけてもらっていた。芸者の生活はお座敷からかかる声にかかっていた。どんなによい芸を持っていてもお声がかからなければ干乾しになってしまう。三味線も弾けないふさこがタチひとつで二十八年も湯河原で芸者を続けてこられたのはあきの存在なくしては考えられなかった。ふさこは恵ホテルの座敷では女中の代わりもやった。
「きょうはふさこ姐さん入ってる?」
「の、ようよ」
「じゃふさこ姐さんにまかせとこうよ」
チーちゃんこと久子もノンちゃんもユキちゃんもいまや恵ホテルの最古参女中になっていた。ふさこはそうした女中からも信任が厚かった。
ある日、恵ホテルに一人の上客が現れた。通しと呼ばれる呼びこみが連れてきた客である。入ってくるなりみんなの前でキッチリ束ねた一万円札の札束を見せ、再び風呂敷に包んでフロントに預けた。
芸者を四人、五人とあげてのドンチャン騒ぎが始まった。むろんふさこも呼ばれた。芸者といわず女中といわず飲めや食えやの大盤振舞い。さすがにあきは不安を覚えてきた。どうもうさん臭い。
そう思うが客商売では誰何するわけにいかない。女中に聞くと景気よく飲み食いするわりにはチップもくれないという。いよいよクサイ。
まごまごするうちに客は「これから熱海行く」といって芸者を引き連れて行ってしまった。
「あすの昼には帰るから」
大金を預けてあるんだ文句あるまいといわんばかりである。
「番頭さん、お札見せてよ」
「駄目ですよ、おかみさん。そんなことしたらお客さんに叱られますよ」
番頭に拒まれてあきは唇を噛んだ。
あくる朝、芸者だけ熱海から帰ってきた。さてこそと風呂敷を解いて札束をバラしてみると上と下の札だけが本物で後はニセモノだった。あききはその二万円だけで客に飲み食いさせた挙句芸者の玉代まで払わなければならないのである。
「おかみさん、あたしは玉代いいですから」
「そうはいかないよ」
あきとふさこは押し問答をした。結局、当日来た芸者の中でふさこだけ玉代を半分泣くことで話がついた。気は心とあきはふさこの気持ちを快く受けることにした。